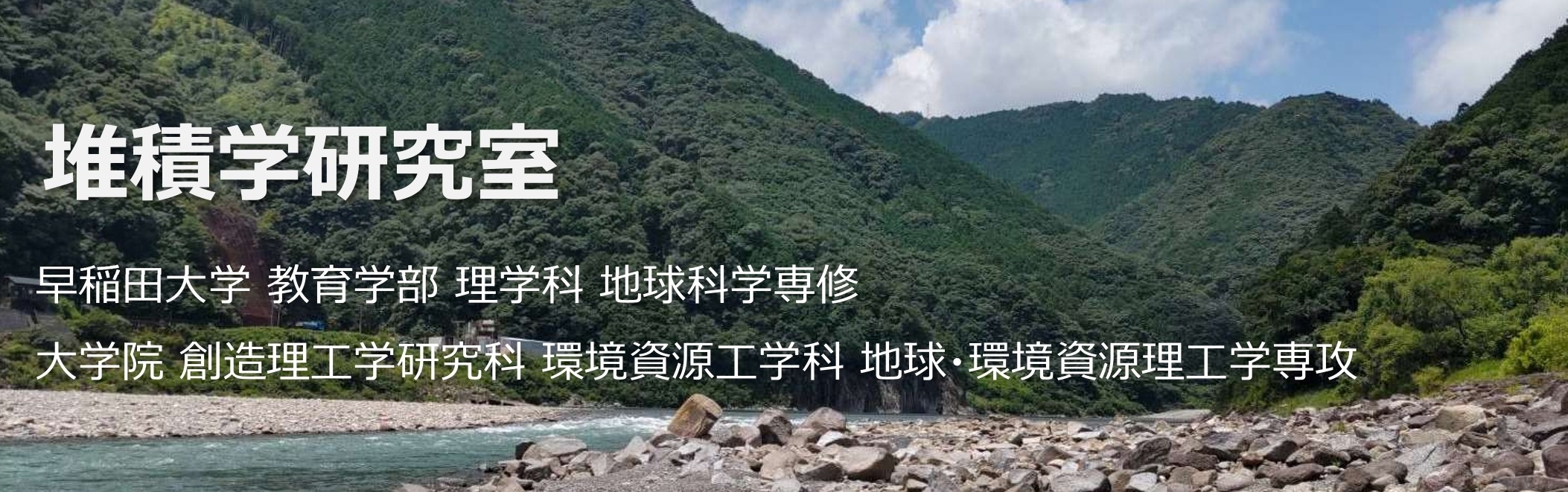研究室紹介
2025度の堆積学研究室は,博士課程の学生4名,修士2年生3名,修士1年生4名,学部4年生10名の計21名で活動しています.また,卒業生の助教や留学生の方も在籍しており,和気あいあいとした楽しい研究室となっています.
以下に堆積学研究室の主な活動内容を紹介します.
全体ゼミ
週に1回の全体ゼミでは,各自の研究進捗を発表します.学生1人あたり年に4回ほど発表の機会があり,発表準備の際は,研究室に泊まる人もいるほど忙しくなります.留学生も理解できるよう,発表スライドは英語で作成しています.
サンプリング活動
研究内容は各学生で異なりますが,サンプリングが必要な場合が多く,各自で採取コースや宿泊先を計画します.年に数回,国内だけでなく,海外でサンプリングを行うこともあり,余った時間で観光することもできるなど,非常に楽しい時間です.
データ分析
採取したサンプルから得られたデータを基に,統計学や機械学習などを用いて分析を行います.専門知識が少なくても心配はいりません.先生や博士課程の先輩方が手厚くサポートしてくれるため,疑問点があれば夜遅い時間でも対応いただくことができ,非常にありがたいです.
学会発表
研究室での主な活動は全体ゼミやサンプリングだけではありません.大学院生以上を中心に,国内外の学会で研究成果を発表する機会があります.昨年はイタリア,本年度は韓国での学会に参加し,来年度はドイツでの学会発表が予定されています.海外発表では英語力の向上にもつながるほか,発表準備を通じて,研究の理解が深まるだけでなく,国際的な視野も広がります.
就職活動
堆積学研究室で学んだ知識を活かして専門職に就く学生もいますが,文系就職を選ぶ方も多くいます.また,研究室のOBが訪問して就職先を紹介してくれる機会もあり,説明会後の食事会などで多くの情報を得ることができます.
研究紹介
百分率(パーセント)形式データの数理
岩石化学組成などに広く用いられる百分率(%)や百万分率(ppm)表記のデータは,組成データ(compositional data)と呼ばれ,実数の比例尺度データと同等には平均値,相関係数,信頼区間の計算や多変量解析などの統計処理が施せないことが知られています(例えばPeason,1897;Aitchison,1986).これは,組成データが定数和制約(constant-sum constraint)と呼ばれる特殊な制約条件を被ることに起因しています.定数和制約というのは,例えば,土砂(A g)の中の泥(x g)・砂(y g)・礫(z g)の混合比率を%で表すとその値(%)の合計が絶対量(g)に関わらず100であるということです.この制約条件を回避して実数のデータとして扱うための方法を研究します.
砕屑粒子の形状解析
砂は岩石から削り取られ,水や氷あるいは風などによって運ばれ,運ばれている過程で砂粒どうしがぶつかりあったり,化学的な作用を受けたりすることによって,そのかたちを変えていきます.砂のかたちは,その砂粒子がどのような運搬過程を経てきたのかという情報を含んでいます.そのため,かたちを定量的に評価する手法は数多く提案されてきました.本研究では,,楕円フーリエ-主成分分析法(Elliptic Fourier – Principal Component Analysis; EF-PCA)によって砕屑物粒形(砂粒子のかたち)を定量的に評価しようとしています.例えば,以下のようなことに取り組んでいます.
・EF-PCAから得られる砕屑物粒形を評価する指標を用いて,堆積場の判別を行う.
・砂岩への応用により,古環境の復元に役立てる.
岩石風化の定量化
風化作用は,地球表層の環境に対して影響を及ぼします.大陸表層の岩石が風化することで大陸表層の化学組成や物理特性が変化しますし,風化作用の結果大陸表層から海洋に栄養塩が供給されて海洋の生物活動へ影響を及ぼします.それらの風化作用の影響度を評価するために岩石の風化の度合いを定量する研究が行われてきました.風化を定量する風化指標は主に2つあり,物理風化指標と化学風化指標です.物理風化指標とは岩石の密度や一軸圧縮強度などを用いた風化指標で,化学風化指標とは岩石の化学組成を用いた風化指標です.Ohta and Arai (2007) では,従来の化学風化指標の問題であった「指標の値が風化前の岩石の組成に影響されてしまい風化作用そのものを定量できない」という点を解決する風化指標W値を開発しています.本研究では,既存の風化指標の問題を解決し,風化作用を定量的に評価する風化指標の開発に取り組んでいます.
土壌化作用の室内実験
白亜紀における海洋無酸素事変(Oceanic Anoxic Events ; OAEs)の発生メカニズムとしてWeissert et al.(1998) が提唱した「風化仮説」という仮説があります.「風化仮説」とは,①白亜紀の地球温暖化と活発な火山活動によって大陸地殻表層における風化作用が増大した ②風化作用の増大により海洋に流出する栄養塩類が増大した ③海洋の富栄養化により第二次生産性が増大した ④第二次生産者が溶存酸素を消費しOAEsを引き起こした,という連鎖反応によってOAEsが発生したとする作業仮説です.このうち,②や③のプロセスが事実であった証拠は出てきていますが,①のプロセスは未だ十分に解明されていません.本研究では,白亜紀の環境を模した条件下で実験的に岩石を風化させ,火山活動の大きさと風化の進行度との関連性を検証します.
月における宇宙風化作用
宇宙風化とは,宇宙空間において太陽風や隕石の衝突によって岩石の物理的特性や化学的特性が変化することです.月表面の岩石に対しても宇宙風化作用が起こっていると考えられており,岩石の色彩から宇宙風化の程度を定量することを目標としています.
カソードルミネッセンスを利用した砕屑性石英粒子の源岩解明
カソードルミネッセンス(Cathodoluminescence, 以下CL)とは,電子線を物質に照射した際に生じる発光現象です.CLの発現には,主として物質に含まれる不純物元素の存在や結晶構造の乱れ(空格子・格子間原子および不整構造など)が大きく関与していることから,ほかの分析手段では難しい極微量の不純物元素の特定や構造欠陥の検出にCLの利用が図られています(鹿山, 2006).本研究では,CL発光を示す鉱物のひとつである石英を用いて源岩解明をおこないます.石英は純粋なSiO2からなり,生成過程により様々な結晶構造を持つので,理論的にはCL発光から岩石種を特定することが可能であると考えられます.岩石種ごとの石英粒子のCL発光の特性の違いから源岩を判別する方法を開発し,その成果を砕屑物中の石英粒子に応用することを目指しています.
北東インド・スィンブーム地塊の発達史(25〜16億年前)
中期原生代(20億年前)の地球自転速度の解明
中生代(2.5〜0.6億年前)におけるヨーロッパ地域の古気候変遷
中生代(2.0~1.0億年前)の九州黒瀬川地域の堆積相解析
陸弧における砕屑物成熟化イベントの時系列変化(1.5〜0.65億年前)
前期白亜紀(1.3億年前)における西アジア大陸の古気候解析
中国新疆ウイグル自治区の北部,ジュンガル盆地に分布する前期白亜紀の地層はTagulu層群と呼ばれ,赤色層と灰色層の互層から成ります.二枚貝・貝形虫・カイエビ・魚類の化石が産出し,その生物相から湖成層と考えられています.その湖成層の色彩や化学組成をもとに,前期白亜紀の古気候を解析します.
前期白亜紀(1.3億年前)におけるハドレー流循環の異変
白亜紀(1.5〜0.6億年前)の海洋無酸素事変の解明
機材紹介
堆積学研究室では,多様な研究を支えるために高度な機器を活用しています.以下は,主に使用している機器や施設の詳細です. これらを活用することで,堆積物や岩石の構造や成分を多角的に解析し,地質学の理解を深めています.以下に堆積学研究室で使用する主な機材を紹介します.
SEM(走査型電子顕微鏡)
SEM(Scanning Electron Microscope)は,堆積物や岩石の微細構造を詳細に観察するための装置です.この装置は,電子ビームをサンプルに照射し,表面から放出される二次電子や反射電子を検出することで高分解能の画像を取得します.また,EDS(エネルギー分散型X線分析)を併用することで,サンプル表面の微小領域の元素組成を定量的に解析することも可能です.これにより,堆積物中の粒子間の接触関係や鉱物の特徴,さらには化学変化を詳細に評価できます.
薄片室
薄片室では,サンプルを顕微鏡観察用の薄片に加工します.サンプルは専用の切断機でスライスされ,その後研磨機を用いて厚さ約30ミクロンまで薄く加工されます.この薄片は,偏光顕微鏡や電子顕微鏡での観察に使用されます.堆積物の層状構造や鉱物の配向,さらには変成作用の影響を直接観察できるため,地質学的なプロセスを理解する上で欠かせない工程です.
粉砕室
粉砕室は,岩石や堆積物を粉末状に加工するための専用設備を備えています.粉砕機では,大型の岩石を均一な粒度の粉末に加工します.これにより,以下のXRF(蛍光X線分析)やXRD(X線回折分析)などの化学・鉱物学的解析に適した試料が得られます.特に,堆積物の詳細な化学組成や鉱物特性を明らかにするために重要です.
XRF(蛍光X線分析装置)
XRF(X-ray Fluorescence)は,堆積物や岩石の化学組成を高精度で分析する装置です.試料にX線を照射することで,各元素が特有の波長の蛍光X線を放出します.この蛍光X線を検出することで,試料中の主要元素や微量元素の含有量を非破壊的に測定できます.堆積環境の変遷や,地質プロセスによる成分変化の解明に役立つ貴重なデータを提供します.
XRD(X線回折装置)
XRD(X-ray Diffraction)は,鉱物の結晶構造を解析するための装置です.試料にX線を照射すると,結晶内の原子配列によって特定の角度でX線が回折されます.この回折パターンを解析することで,試料中の鉱物の種類や結晶構造を特定し,含有量を定量的に評価できます.堆積環境や変成条件の推定に欠かせません.
CL(カソードルミネッセンス)
CL(Cathodoluminescence)は,鉱物や堆積物の光学特性を観察するための装置です.サンプルに電子ビームを照射すると,特定の鉱物が発光する現象を利用します.特に石英や方解石などの鉱物が,成長履歴や再結晶化の痕跡を示す発光パターンを観察できます.この技術は,堆積環境の再構築や鉱物の形成過程の解明に有用です.また,微小構造の分析や鉱物の年代測定にも応用されることがあります.CL画像は肉眼で確認できない情報を提供し,研究の新たな視点をもたらします.